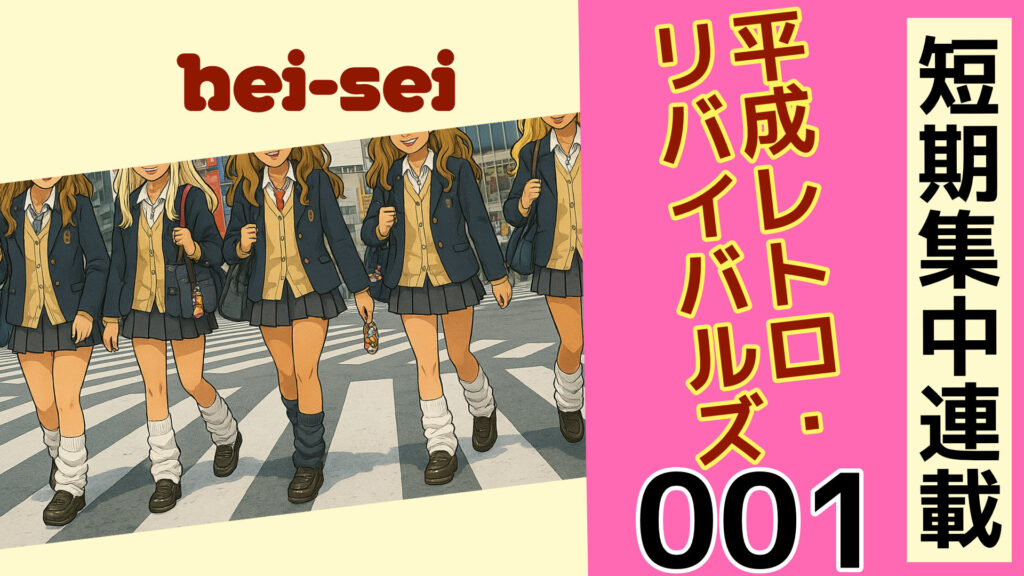前回、私たちは原宿ファッションの魂が形を変え、世界中で生き続けている様を追った。今回は、私たちの日常に深く根ざした「記録」という行為、すなわち「写真」の世界に潜む平成レトロを探求したい。
ポケットの中のスマートフォンは、今や数年前のプロ用機材に匹敵する性能を持つ。誰でも、いつでも、どこでも、高画質で完璧な写真を撮れる時代。しかし、その潮流に逆行するかのように、Z世代の若者たちが夢中になっているものがある。
フィルムを巻く音、粗い画質、強すぎるフラッシュ。それは「写ルンです」に代表される使い捨てカメラであり、少し前まで中古ショップの片隅に追いやられていた平成のコンパクトデジタルカメラ(オールドデジカメ)だ。そして、撮った写真をシールにして交換し合った、あのプリクラとプリクラ帳の文化である。
なぜ彼らは、圧倒的に便利なスマホカメラを横目に、あえて「不便」な道具を選ぶのか。その答えは、現代のデジタル社会が見失いがちな「体験価値」と、新しい自己表現の形にあった。
撮り直せない一瞬の価値 – 使い捨てカメラの「時間差攻撃」
まず、使い捨てカメラの魅力から見ていこう。その本質は「不確実性」と「待つ時間」にある。
スマホなら、撮った瞬間に写真を確認し、気に入らなければ何度でも撮り直せる。しかし、使い捨てカメラは違う。シャッターを切れば、もう後戻りはできない。フィルムをすべて撮り終え、現像に出すまで、何が写っているかは誰にも分からないのだ。
この「撮り直しが効かない」という制約が、シャッターを押す一瞬一瞬を特別なものに変える。そして、数日後に現像された写真と対面した時、忘れていた光景や感情が、像が甘く、少し光が漏れた(感光した)独特の風合いと共に蘇る。この時間差で届く感動こそが、最大の“エモポイント”なのだ。それは、効率や完璧さとは真逆の、贅沢な体験と言える。
“盛れない”が心地いい – オールドデジカメの「生々しい」記録
使い捨てカメラのブームに続き、今、Z世代の心を掴んでいるのが、2000年代に普及した「オールドデジカメ」だ。
スマホのカメラが、AIによって肌を滑らかにし、食べ物を美味しそうに見せ、暗い場所でも明るく写す「補正上手の優等生」だとすれば、オールドデジカメは「少し不器用で正直な転校生」である。
・青みがかった独特の色味
・被写体を白く飛ばす、容赦ないフラッシュ
・ざらついた、決して高精細ではない画質
これらの「欠点」が、スマホが見せてくれる“綺麗すぎる”世界とは違う、生々しくてリアルな空気感を写し出す。そこには、加工アプリで作られた「カワイイ」とは異なる、ありのままの魅力が宿る。友人との何気ない日常をオールドデジカメで撮る行為は、「盛る」ことから解放された、心地よい自己表現なのだ。
共有する「時間」そのもの – プリクラ帳という名の友情の証
そして、このアナログ回帰の潮流は、プリクラ文化の再燃にも繋がっている。
最新のプリクラは、驚くほどに目が大きく、足が長くなる「超絶盛り」機能が当たり前だ。しかし若者たちが価値を見出しているのは、その加工技術だけではない。むしろ、撮影から落書き、シールを分け合うまでの一連の体験そのものだ。
狭いブースに友人たちとぎゅうぎゅう詰めで入り、ポーズに悩み、制限時間内に焦りながらペンで落書きをする。完成したシールをハサミで切り分け、自分のプリクラ帳に貼るだけでなく、友達のプリクラ帳にも貼ってあげる。
スマホのデータフォルダに眠る無数の写真と違い、プリクラ帳は物理的な「モノ」として、友情の歴史を刻んでいく。ページをめくるたびに、その日一緒に笑い合った時間や空気感が蘇る。デジタルでは得られない、この手触りのあるコミュニケーションこそが、プリクラが絶えず愛される理由なのである。
私たちが本当に記録したいもの
使い捨てカメラ、オールドデジカメ、プリクラ帳。これら平成レトロガジェットのリバイバルが示すのは、私たちが写真に求めるものが、単なる「綺麗な画像データ」だけではなくなったという事実だ。
あえて不便な道具を選ぶ行為は、結果だけでなくプロセスを楽しみ、予測不能な偶然を愛し、仲間との時間を形として残したいという、人間的な欲求の表れなのかもしれない。
完璧な画像が無限に生産される時代だからこそ、少し不器用で、たった一つしかない「体験の証」が、私たちの心を強く揺さぶるのだ。
(第5回へつづく)