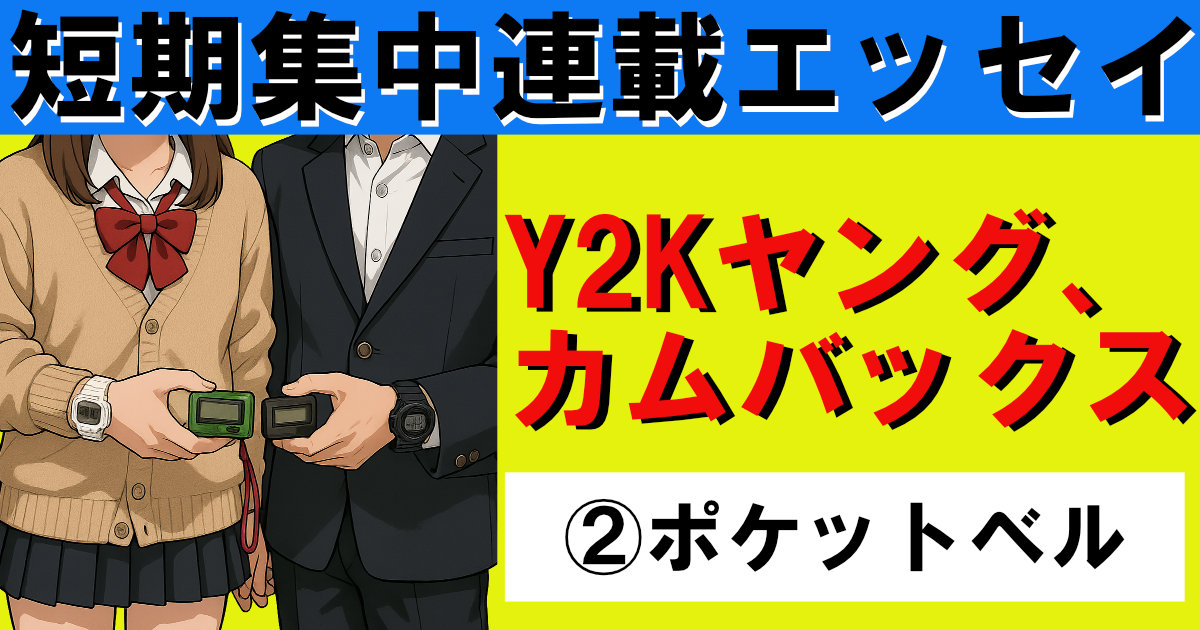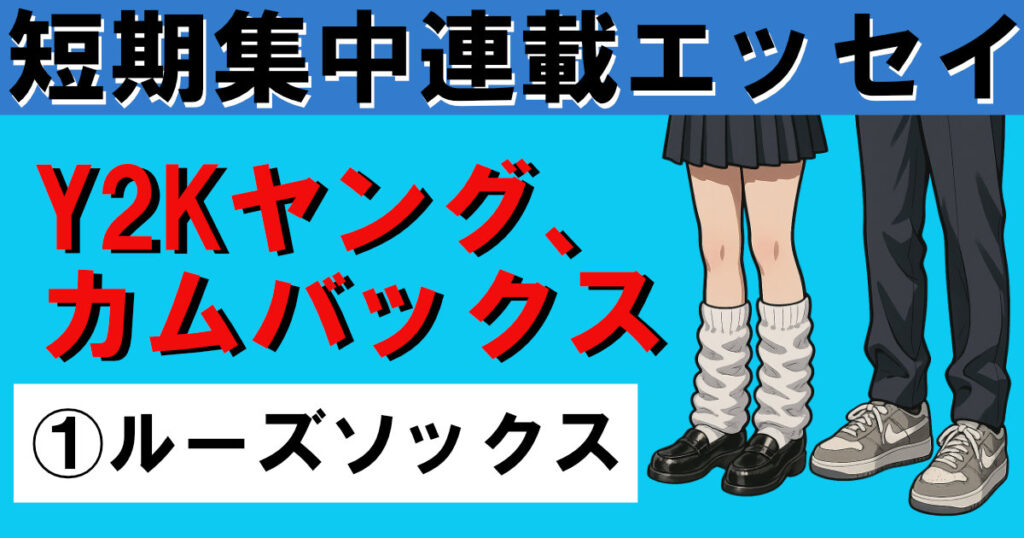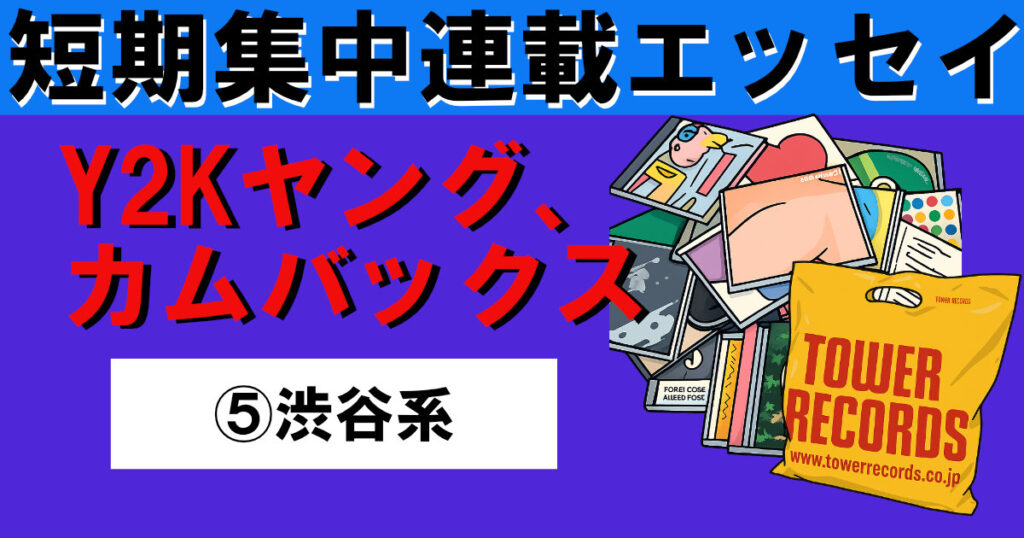「2000年代の若者」。その言葉の響きを聞いて、あなたはどんなイメージを抱くだろうか?
四半世紀前の出来事。とにかく若者が勢いのあった時代。
僕らは、ノストラダムスの根拠のない予言を半分信じて、半分反抗して、この世の中が続いても続かなくてもいいのになんて社会に対する責任感なんて持っていなかった。
結果、Y2K(2000年代)とは、時代の一区切りだった。
でも、時代の一区切りだけで、あんなファッションやカルチャーやデジタルツールが流行ったのか?
いや、「さき行っとくぜ、新世紀!」とも言えるように、すでに用意されていたファッションやカルチャーやデジタルツールが盛り上げてくれていたかのようにも思えて仕方がない。
1980年生まれのワタナベミツテルが、素通りしてきたY2Kを物語る、そんなエッセイの第2回目は、ポケベル。
渋谷系音楽のBGMで、タコ公園の滑り台をすべって降りてきた女子高生ヒロスエのCM。
「ヒロスエリョウコがポケベル始めるんだとよ。ワンダフルプライス?ってどれだけだよ。」
あれは衝撃的なCMだった。ポケベルは、すでにサラリーマンの呼び出しアイテムとして浸透していたのだが、高校生のお小遣いで持てるようになったという時代の幕開けだったんだ。
その波も徐々に浸透していき、僕らの身近では高校の校舎にポケベルを持ち込むギャルの皆さん。そのギャルの彼氏が、彼女に迫られてポケベルを持ったり。
いまの現代ではもう巷(ちまた)では数が減ってしまった公衆電話も、当時はかなり機能していた。ポケベルを打つために、公衆電話が女子高生の待ち行列で並んでいた。テレカ(テレホンカード)もまだ現役バリバリに機能していた。
ただ、いまのスマホやひと世代前のガラケーとは違い、公衆電話や自宅の電話に#のボタンがないと機能がしなかった。
ポケベルは基本的に数字しか表示できないため、「数字の語呂合わせ」を使ってメッセージを送るのが主流だった。
0840 = おはよう (Ohayou – Good morning)
0906 = おくれる (Okureru – I’ll be late)
4649 = よろしく (Yoroshiku – Nice to meet you / Please treat me well)
889 = はやく (Hayaku – Hurry up / Quickly)
14106 = あいしてる (Aishiteru – I love you)
3470 = さよなら (Sayonara – Goodbye)
ポケベルを持っていること自体が、ある種のステータスであり、友人関係を維持するための重要な要素だった。持っていないと仲間外れにされるような感覚を持つ生徒もいた。
ただ、ポケベルの数字の語呂合わせを覚えるよりも、たくさん覚えるはずのことがあった高校生。
コミュニケーションツールとして、これから使っていくアイテムだから、みんなが覚えるのに必死だったのは致し方ない。
ポケベル本体を持つための月額料金が1,980円から2,980円だったので、世のお父さんお母さんは反対をしなかったのだが。
お父さんお母さんが、娘や息子が自宅の電話で友達に、ポケベルを打つ速さを見て、前の月の電話料金の請求書を見て、驚愕(きょうがく)した家族もあったようだ。
僕の友人の自宅の電話器は、そのために#ボタンが破壊されていた。母親の犯行らしい。